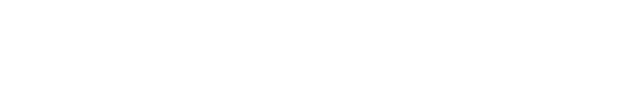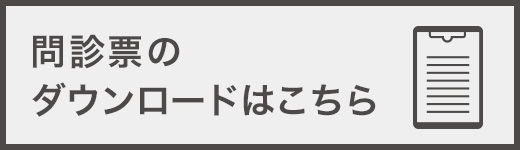耳管開放症・狭窄症(自分の声がひびく、耳がつまる)
耳管関連で受診の際には、当院の問診票および耳管外来問診票を印刷して、可能な限り詳細に記入後、お持ちくださると適切な診療につながりやすくなるので助かります。関係のないようなことでも遠慮なく記入ください。印刷のできない方は、受付窓口で「耳管診療」を希望の旨を伝えてください。
耳管疾患の診療をご希望の方は、聴覚検査と耳管機能検査JK-05A(Dタイプ)を先に案内することがありますことをご了承ください。
- 耳管機能検査JK-05A(Dタイプ)
この検査は高機能のタイプです。音響耳管法(sonotubometry)および耳管鼓室気流動態(tubotympanoaerodynamic graphy : TTAG)法、加圧減圧法(inflation―deflation test)を行うことができます。また、場合によって音響耳管法を座位と前屈位で行うことでより耳管開放症の診断精度を上げます。さらに音響耳管法で異常を認めなかった場合でも耳管鼓室気流動態法を用いることによって診断できる場合があります。状況や症状、どのレベルでの治療をご希望されるかによって検査の程度は相談させてください。
耳管とは?
中耳と呼ばれる部位と鼻咽腔をつなぐ管のことです。大気から中耳にかかる圧力を調節する働きがあります。正常な状態では閉じており、口を開ける動作である「あくび」をしたり、つばを飲み込んだりしたときだけ耳管が開きます。
耳管の開放の度合いは人それぞれです。耳管が狭くなり、中耳の圧調整がうまくいかなくなるものが耳管狭窄症、必要以上に開いているのが耳管開放症です。高い山に登ったり、エレベーターで上昇したり、飛行機に乗ったりすると耳がつまったような感じがして、あくびや唾を飲み込むことで治った経験があるかと思います。これが耳管の開放による圧力の調節です。
耳管開放症とは?
耳管が開くことで不快な症状が出現した状態です。
■原因
ストレス・睡眠不足、体重減少、加齢(70歳代に1つのピークがあります)、妊娠・産後、経口ピル(薬を変えると改善することがあります)、中耳炎、など様々です。原因不明であることも多いです。
■症状
耳がカサカサ・ガサガサする、ポコポコ・ボコボコする、バリバリする、自分の声が耳に響いてうるさい(自声強聴)、耳がふさがった感じがする(耳閉感)、自分の呼吸音が響いて聞こえる(自己呼吸音聴取)、などがあります。これらの症状は他の耳疾患においても出現することがありますが、耳管開放症は横になったり、頭を下げると改善します。立ち仕事が続いたり、運動や脱水などにより悪化する傾向があります。1-2時間程の歌唱によっても出現することがあります。他人の声や機械音、金属音が過剰に響いて聞こえるときは難聴による症状であることがあります。問診や聴覚および耳管機能検査などで診断させていただきます。
■診断
典型的な方では、鼓膜が鼻呼吸とともに動揺します。その他、耳管機能検査や側頭骨CT検査、聴覚検査、など種々の検査を総合して診断します。耳管開放症は常に症状や所見がみられる疾患ではないので、問診が非常に重要な診断の手がかりであり、検査を反復することが必要な場合も多いです。また、下記治療を行いながら、その治療効果を聞きながら診断することもあります。
■治療
重症度に応じて、生活指導、点鼻療法や漢方療法、耳管処置、手術療法を選択します。一般的には、まず生活指導、点鼻薬、内服治療を試し、効果が不十分な場合にその他の治療へ進みます。
-
生活指導
やせの改善・予防、水分補給、スカーフ療法(スカーフを首に巻く)など があります。激しい運動をした後の他、気温が低くなった時、乾燥している時などには症状が増悪することが多いです。運動前後には適切な水分補給、マスクをして保温・保湿に努めることも効果がある場合があります。頸部圧迫(男性ならネクタイ、女性ならスカーフやハイネックのセーターなど)により耳管周辺にむくみを生じさせると症状が軽減します。ただし、強く締めすぎると気を失うこともありますので、注意が必要です。
鼻をすすると症状が改善することがありますが、後に真珠腫性中耳炎や癒着性中耳炎といった手術が必要な中耳炎に移行することがあります。鼻すすりは控えることを勧めています。
-
点鼻療法
症状のある側の鼻から生理食塩水を垂らします。心不全や腎不全で塩分制限がある場合を除き、副作用はほとんどないので手軽に行える治療法です。慣れるまでに時間がかかる、効果が短時間であるという欠点もありますが、気軽に行える治療法です。
-
漢方療法
補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、加味帰脾湯(かみきひとう)、など状況に応じた処方薬を食前に内服します。加味帰脾湯は1-2週間の内服で効果を感じることが多いです。ドラッグストアなどの商品は病院での処方薬よりも成分量が少ないことがありますので、ドラッグストアの商品で効果が無かったとしても、ぜひ処方薬を試してみることを勧めています。また同じ名前の処方薬の中でも、製造会社が異なると効果に差を感じる方がいるので、相談しながら処方させていただきます。
-
鼓膜パッチ
呼吸により動揺する鼓膜にテープなどを張り、耳管開放症状をやわらげるものです。気軽に行えますが、テープのずれや乾燥などに対応する必要もあります。
-
耳管処置
鼻から金属の管を通し、医療用ゼリーなどを耳管に直接注入します。医療用ゼリーの注入は診断のために行うこともあります。効果は人それぞれですが、1日~14日の効果が持続することがあります。少し痛みを伴う治療法なので、とても有効な治療法ですが、処置は軽めから始めることが多いです。
-
耳管ピン挿入術(当院で導入しています)
上記の保存的治療療法を行っても症状が改善せず、かつ診断時に明らかな耳管開放所見がみられる場合に選択します。正常な聴力の方の聴力を低下させ得る手術になり得ります。保険適応の手術になりますが、比較的新規治療のため高額です。そのため、手術によるメリットとデメリットをよく相談した上での治療となります。また、ピンの挿入ができずに手術を中止することもあります。
(参考:日本大学医学部耳鼻咽喉科 耳管外来)
主な関連学会:日本耳科学会
耳管狭窄症とは?
耳管狭窄症には機能的と器質的があります。
機能的狭窄とは、鼻の奥の耳管の入り口から空気を通す処置などで開くが、唾のみのような動作によっては耳管が開きにくい状態です。耳管機能検査では、外耳道音圧が上昇しないことで狭窄を疑います。しかしながら、これだけで狭窄症と診断することはできませんので、総合的に診断いたします。
器質的狭窄とは、処置や唾のみでも耳管が開かない状態です。耳管機能検査で調べることが出来ますが、正常な方でも狭窄の検査結果を示す方がいますので、こちらも総合的に診断いたします。
原因:感冒、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎が原因であることが多いです。またアデノイド増殖症、腫瘍のこともありますので鼻からの内視鏡検査で確認させていただいています。加齢によることも多いです。
症状:耳閉感(耳づまり)、難聴感、山に登っている感じが続く、水が入っているよう、耳鳴り、耳の痛み、などがあります。
診断:受診時に症状が無いことも多く、問診や聴覚検査、耳管機能検査、耳管通気法などを用いて総合的に診断します。子供の頃に中耳炎に罹患していた方が多いです。
治療:症状の強さと原因に応じて相談させていただきます。自己換気の案内、投薬(内服、漢方)、耳管通気、鼓膜切開術・鼓膜換気チューブ留置術、などを提案させていただいています。当院ではバルーンによる耳管開大術はおこなっていないため、適応となる方には紹介状を用意します。
滲出性中耳炎の再発の予測
滲出性中耳炎に対して鼓膜チューブを留置し、改善した場合には、そのチューブの抜去の可否について注意を要します。当院で用いている耳管機能検査ではチューブ抜去後の滲出性中耳炎の再発予測を行うことが出来ます。
スキューバダイビングや飛行機への搭乗の適応
まずは耳抜きが出来ること、または、唾をのむことで耳管が開けば、ダイビングや飛行機の搭乗でトラブルを起こす可能性は低くなります。さらに当院の耳管機能検査では、耳管の開きぐあいを客観的に評価できるため、ダイビングや飛行機への搭乗の可否の判断をすることができます。しかしながら、感冒などで状況は変わるため、可否を完全に保証することは出来ないことには注意が必要です。
耳管外来の診療の流れ
- 診療時間内に当院に来院し、耳管診療希望の旨をお伝えください。
- 事前に本ページ最初の文にある問診表をダウンロード、印刷し、当日お持ちください。印刷できない場合は早めに当院にお越しになってください。来院後、問診表を渡します。情報量が多いと助かりますので、些細なことも含めて詳細にお書きになってください。
- 追加で病状を伺い、診察をします。以前の聴力検査をお持ちの方は持参ください。無い場合はまず聴覚検査(聴力検査、鼓膜の動きの検査、など)をします。
- 耳管機能検査JK-05A(Dタイプ)で必要に応じた検査を行います。
- 診断にもよりますが、まずは内服、耳管へのジェル注入などの相談をし、治療を開始します。